木浪真由美 的「青森りんご物語」①
はじめに りんご―それは「生きた歴史遺産」
明治維新で仕事を無くした藩士たちの、失業対策で始まった、青森県のりんご栽培。
生産量日本一のりんご産地に、こんな歴史がある事は、意外に知られていないのではないでしょうか?
今年二〇二五年は、青森県にりんごがやって来て一五〇周年にあたります。
一八七五年春、青森県庁に三本のりんごの苗木が届き、ある一人の元弘前藩士が、その苗木を敷地内に植えました。その人こそ、りんご栽培のパイオニアとして七二歳までの人生を、りんごをはじめとする農産物一筋に生きていく菊池楯衛(きくちたてえ)です。この物語は、この菊池から始まる青森県りんご栽培の壮大な遺産です。
こんな歴史があったなんて知っていたら、りんごを買う時、もっと真剣勝負だったかもしれない。そう思っていただけたら嬉しいです。そして、この本を読み終えた頃には、りんごを食べずには、いられなくなるでしょう。あなたにとって「単なる果物」だったりんごが、「生きた歴史遺産」であることに、気づいてしまったからです。
菊池楯衛を筆頭に始まるりんご栽培の歴史ですが、彼一人が英雄なわけではありません。これからお話をしていく、青森をりんご王国にした立役者たちを、ご紹介しましょう。
弘前藩一二代藩主である津軽承昭(つぐあきら)、青森みちのく銀行、株式会社カクヒロなどをつくった弘前藩家老大道寺繁禎(しげよし)、そしてもう一人の家老であり、石田三成の子孫である杉山成知(なりとも)、りんご栽培というスタートアップが実現できたのは、代表してこの四人の存在が大きいと思っています。
そして日本人として、最も早くりんごを作って食べていた、と言われる松平春嶽、七飯に巨大な果樹園をつくったドイツ人ガルトネル、菊池楯衛に接木法を伝授したアメリカ人技師ルイス・ベーマー。彼らの存在無くして、日本にりんごは根付かなかったかもしれません。
後に青山学院院長となる本多庸一が、横浜から弘前へ連れて帰ったジョン・イングは、当時、東北で唯一、外国人宣教師を雇用していた東奥義塾で教鞭をとり、生徒たちにりんごを食べさせました。その東奥義塾や東奥日報を創設した菊池九郎。そして弟の菊池三郎は、つがる市柏に現存する、日本最古のりんごの木を譲った人だと言われています。
大道寺と一緒に酪農会社を運営した、笹森儀助(ささもりぎすけ)は、のちに国防を憂いて日本中を探検、『南嶋探検』『千島探検』などの著書を残しました。この本は現場を見て書いた国防書として、柳田國男にも影響を与え、更に、明治天皇も読んだと言われています。
この笹森に、人格形成において、大きな影響を受けた外崎嘉七(とのさきかしち)は、東北各地へ指導に出向き、りんごの神様と呼ばれる指導者になっていきます。
その外崎が盟友としたのは、のちに北海道大学学長となっていく島義鄰(しま よしちか)と、晩年、大連に渡り大陸に津軽式りんご栽培を伝授する楠美冬次郎(くすみとうじろう)(*)、そして農家の地位向上に尽力し、組合という概念を実践した豪農相馬貞一(そうまていいち)、この流れは続編で紹介する木村甚彌(きむらじんや)へと繋がっていきます。
(*)楠美冬次郎の読み方に関しましては『青森県人名大辞典』を引用し「くすみとうじろう」としました。
りんごは冷害に強く、高値で取引されるため、多くの資産家が投資対象としました。
黒石の貴族院議員で、名勝金平成園施主の加藤宇兵衛(かとううへい)、りんご協会を創った、澁川傅次郎(しぶかわでんじろう)の祖父・澁川伝蔵(しぶかわでんぞう)、本多庸一に導かれ、藤崎教会をつくった佐藤勝三郎、りんご農家の副業として、馬鈴薯作りを推奨した藤本徹郎らについても特筆しました。
このように、今回の津軽地方前編の登場人物を、列挙してみましたが、この本では彼らが織りなす歴史を、できるだけ時系列で書いてみました。マニアックな地名が出て来ますが、できるだけインターネットで検索しながら、読んで頂くと印象に残りやすいかと思います。
また、現地にて「とことん!りんごの歴史ツアー」を開催中です(令和七年現在)。
是非、ご参加ください。https://matatabi-club.com/tour/3040.html
続編は明治後期から昭和五〇年代の、ふじりんごが台頭してくる頃までを書き上げる予定です。更に、青森県南部地方のりんご栽培の歴史も、とても興味深いので只今調査中です。いずれしっかりと書き上げたいと思いますので、もう少しお待ちください。
私の手元には『りんご百年史』という本があります。厚さ七センチメートルの大きな本です。これは今から五〇年前、青森りんご百年記念事業会が発刊したもので、とても貴重な本です。普通の図書館では、館外持ち出しできないので、借りて来ることができません。
毎朝三時起床の私は、朝方調べものに集中したい一心で、インターネットでこれを見つけて買いました。書き込みしたりインデックスを張り付けたり、一日に何度も開くのできっとそのうちボロボロになるでしょう。この世を去る時はくたくたにして、頭に詰め込んでいこうと思っています。
りんご栽培に関する細かい情報はこの本から確認をとっていますし、読み物としても飽きる事がありません。永遠に読んでいられる一冊です。この本に書いてあることをわかりやすく伝える役目が自分だと考えております。
歴史とは、過去に生きた先人たちが、繰り返してきた選択の結果です。何を選び何を捨てて来たのか、どうしてそう決めたのか、何を願っていたのか。これら一つ一つの歴史は私たちの体の一部となっているのです。ですから、歴史には共感できる場面、自分事と感じる場面があるのかもしれません。この本の中にもそんな奇跡が入っていたら嬉しいです。
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
PRODUCTS
りんごの歴史を伝承していく為の各種ツール・サービスを開発しています。
遊び方解説書(日本語)はこちらから印刷できます
遊び方解説書(英語)はこちらから印刷できます
EVENTS
イベントによりりんごの歴史がより身近なるようご案内させていただきます。


NEWS
PRODUCTSやりんごの歴史など様々なコンテンツの発信をします。
7/22,7/23『ぷらすマルシェ』に出展
りんご歴史研究所の木浪です。 来週7月22日23日平川市猿賀公園で行われる「ぷらすマルシェ」に当研究所も参加します。 猿賀公園の蓮の花は平川市観光協会が毎日動画を配信しているので、咲き具合を確認できます。https://hirakawa-kankou.com/2020/10/22/sarukakouen/ 去年のぷらすマルシェは天候にも恵まれ、4000人に迫るの人出となりました。今年も盛況となりますように。...
紙芝居を製作中
りんご栽培の歴史を子供たちに話す時やっぱり紙芝居かなっと思い製作中です。原稿がことのほか上手くまとまったのでこちらに投稿します。紙芝居で子供たちにお話しするときはもっと簡単な言葉を使いますがこれが難しそう!練習します。 「青森にりんごがやってきた!菊池楯衛の物語」 1, 今から148年前青森県に初めて西洋リンゴがや って来ました。 それまでは和りんごという小さくてあまり甘くな いりんごしかありませんでした。 2,...
りんご歴史研究所が生まれたのは
りんご歴史研究所が生まれたのはNext AOMORIがあったから。 それまで青森県のりんご栽培に全く興味はありませんでした。その割りに大それた名前を付けてごめんなさい。これからしっかり勉強して行きます。兎に角、私の中に隠れていたものを取り出してくれたNext AOMORIの仲間達。ありがとう! Next AOMORIとは、私にとって人生のクロスロードでした。本当に素晴らしいプログラムです。未来の話をしたい人におすすめします。...
【りんご歴史研究所】ホームページを開設しました
りんご歴史研究所始動! 青森といえば”りんご”。”りんご”といえば青森。 このように聞くと皆さんはイメージしやすいですか? おそらく青森県内、県外のすべての方々がりんごと聞くと青森県をイメージしていただけると思います。しかし、りんごが初めて青森県に持ち込まれた当初は苦難の連続だったと伝えられています。先人たちの並外れた努力と挑戦によりりんごは青森県へと根付きました。 【りんご歴史研究所】はそんな先人たちの挑戦を後世に伝えると共に、青森で未来に向けて挑戦する方々を応援していくために設立されました。...
公式Facebook
STORY
りんごを青森県に根づかせた先人のストーリー
新たな時代の幕開け

大政奉還により新しい時代の幕開けとなった明治時代
幕府および藩の解体により、特にこれまで武士として生きてきた人々には大きな影響を与えました。そんな激動の時代の中、新たな産業の創出を夢見て青森県にりんごが持ち込まれました。
しかし、豪雪地帯青森県はりんごの生産に適した土地ではなかったのです。

時代の移り変わりはいつも突然訪れます。
明治時代に入り、特に今まで武士として生きてきた人達は明日からいったいどう生きていけばいいんだ!と悩みもがいてました。
そんな中、耳にした『りんご栽培』という新たな産業。明日への希望を『りんご』に託して、魂である刀を剪定鋸、鋏に持ち換え先人たちの挑戦がスタートしました。
先人たちの挑戦
先駆者

江戸時代末期に津軽藩(現在の青森県津軽地方)の武士家系に生まれた『菊池楯衛(きくちたてえ)』は、新たな産業『りんご栽培』の話を聞き衝撃を受けました。
これが自分の生きる道だと思い立った菊池は北海道に渡り、アメリカ人の農業技師より果樹栽培の技術を学び、自身でもりんご栽培の手法を研究しました。
菊池は弘前に戻り化育社という組織を設立。農業を志す仲間達に自身が確立したりんご栽培の手法を広めました。
この菊池の活動が現在の青森県のりんご産業の礎になったと言われています。

りんご栽培を青森県に根づかせた先人達。
今までの常識が刻一刻と塗り替えられていく現在の世の中、先人達の挑戦は私たちに勇気と希望を与えてくれます。
そんな先人達の挑戦を後世に伝え、これから挑戦していく人達を応援したいとの思いから『りんご歴史研究所』は設立されました。
私たちの活動を通してこれから青森県で未来のために挑戦する人々が一人でも増えていくことを心から願っています。
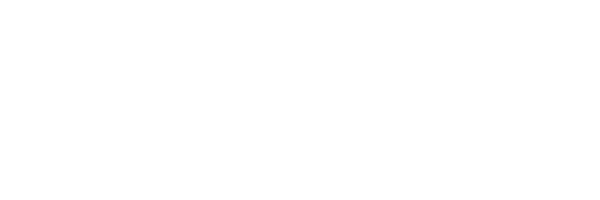
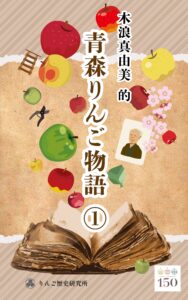


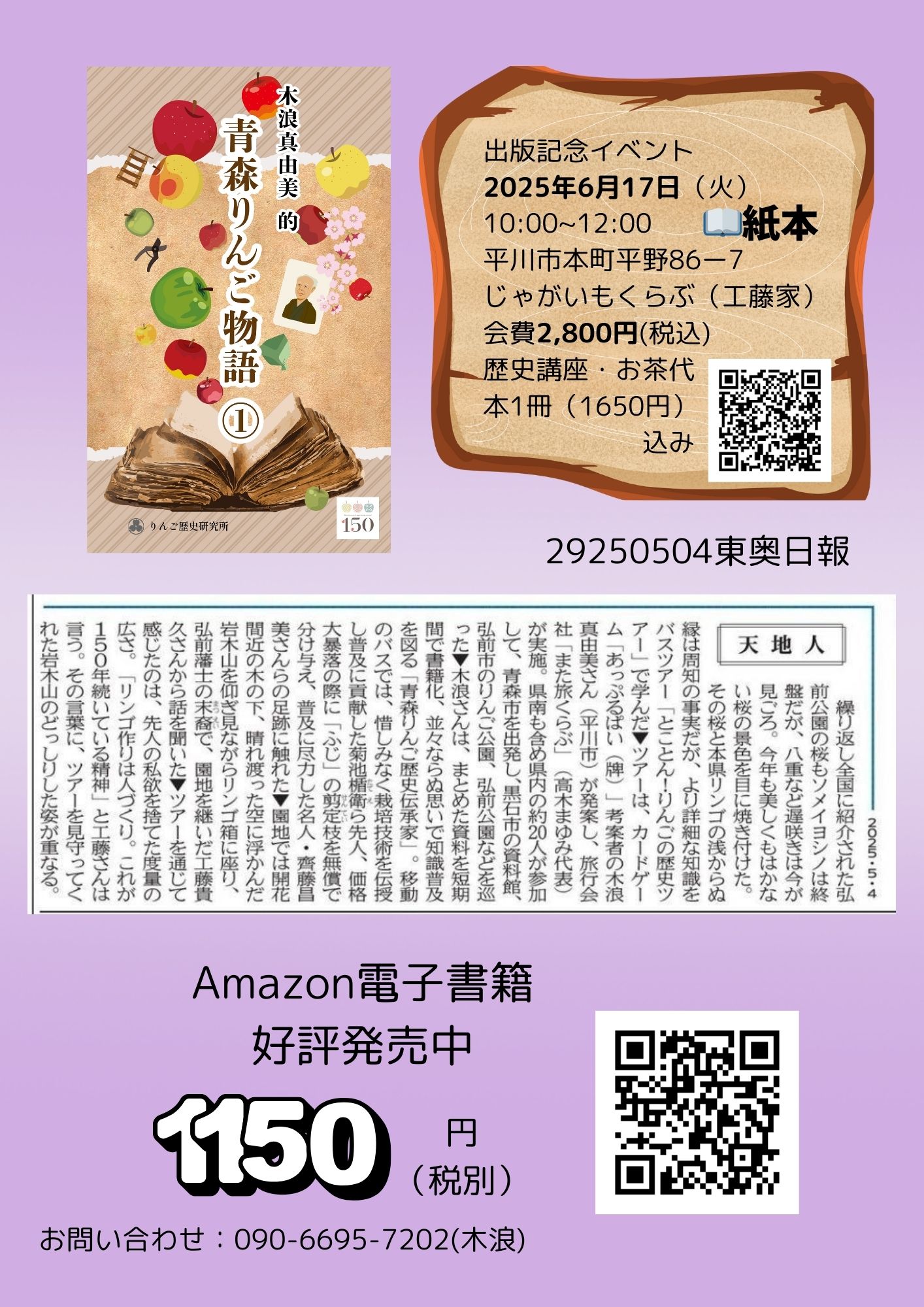
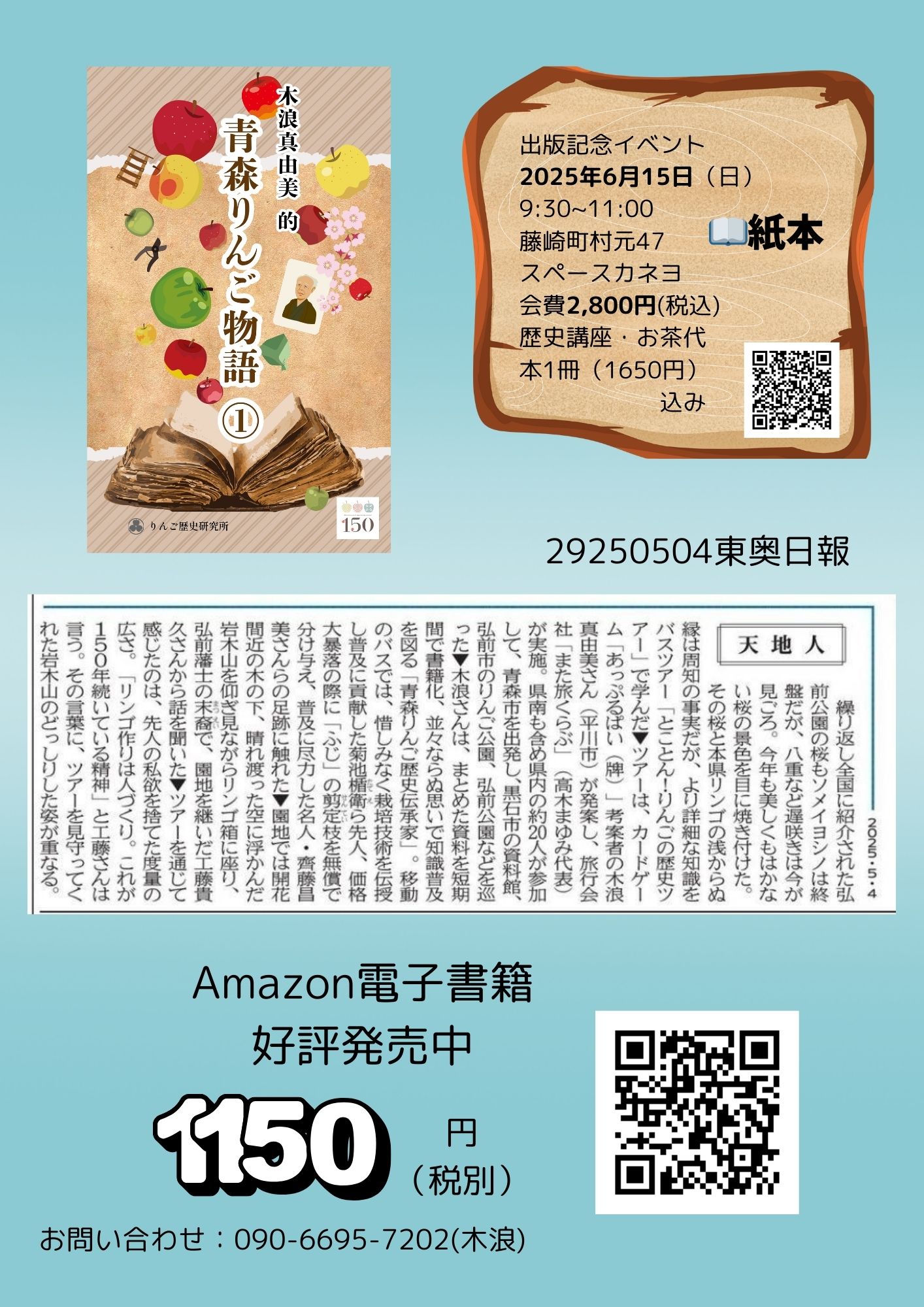
大会チラシ-scaled.jpg)



表-scaled.jpg)
裏-scaled.jpg)























世界選手権大会FB画像.png)








